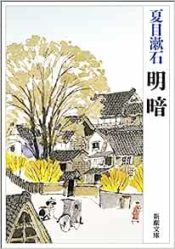読めば読むほど味が出る、未完の傑作
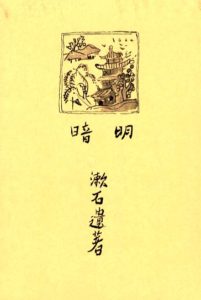
言わずと知れた夏目漱石(1867〈慶応3〉年2月9日 – 1916〈大正5〉年12月9日)最後の作品です。
執筆途中に漱石が亡くなったため、絶筆となりました。
物語はまだまだ先を感じさせる意味深な雰囲気で終わりますが、それがかえってラストにふさわしいと言う人もいます。一方で、先を読みたいと言う願望は漱石の死後もずっと燻ぶり続け、ついに水村美苗さんという方による続編も生まれました。
ストーリーは世間的には「良い夫婦」でも、どこか噛み合わないふたりと、そこに不意に現れる「女」との三角関係未遂を描いたもの。面白いのは、ただそれだけでなく、病的なおせっかいや嫉妬にまみれた様々な魑魅魍魎が本筋に絡んできて、まさに百鬼夜行の相を呈しているところです。
トルストイの「戦争と平和」には、いわゆる毒親・モンスターペアレントの最終形態のようなドルベツカーヤ公爵夫人が出てきますし、ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」には香ばしい醜悪さを放つコーリャという悪ガキが登場しますが、「明暗」の吉川夫人と小林もこれらに匹敵する面倒くささをまき散らします。
他にも吉川、お秀…。
いや、主人公の津田とお延だって、万能の人間ではありません。それに津田が思いを断ち切れない清子だって、ただただ天然のキャラクターで、言うほどの「いい女」などではない。
同じ三角関係でも、Kと先生がお嬢さんを取り合って、Kが血しぶきあげて自殺して、乃木大将の殉死に合わせて先生も死んだ「こころ」の劇的迫力とは対照的なもどかしさです。
ちなみに、私がこの小説を初めて読んだのは平成の初めころ。まだバブルが終わった感も乏しく、テレビでは毎日タレントがバカ騒ぎし、音楽シーンも華やかで爛熟の極み。まさに皆が平和で良い時代を謳歌していて、このじめじめした人間模様を素直に楽しむことはできませんでした。
しかし、徐々に日本衰退の歪みが随所に現れるようになり、政府も「自助努力」の掛け声のもとに国民の庇護が放棄されつつある現在、この「明暗」の世界観はとてもリアルな描写として心に引っかかってきます。
例えば、どうしようもない性格の小林が津田に対して哭くシーンがあります。津田は「それから」の代助のような高等遊民ではなく、痔の手術代にも事欠く庶民ですが、小林から見れば鼻持ちならない勝ち組であり、自分の境遇のみじめさが堪らなかったのでしょう。
「そらあの通りだ。上流社会のように高慢ちきな人間は一人もいやしない」
「じゃ僕はどうすればいいんだ。どうすれば君から尊敬されるんだ。後生だから教えてくれ。僕はこれでも君から尊敬されたいんだ」
と被害妄想的に愚痴ります。ただ、そんな小林に言い放った津田の言葉もまた印象的。
「君見たいにむやみに上流社会の悪口をいうと、さっそく社会主義者と間違えられるぞ。少し用心しろ」
何だかネット上で頻繁に見かけるやりとりに似ていますね。
令和になって、世代間の分断や勝ち組・負け組のカテゴライズが行われ、この「明暗」の時代と同じ、じめじめした対立感情はあちこちに存在しています。
イェール大学アシスタント・プロフェッサー、成田悠輔さんは、日本そのものが没落しているのに、コップの中で無益な対立が絶え間なく起きている、と喝破していますが、明治末期も似たような世相だったのでしょう。
とはいえ、「明暗」の世界はドストエフスキーやカフカ、魯迅の小説に出てくるような、絶望的な貧しさを感じるものではなく、モダンな洋館が出て来たり、おでんで一杯やったり、湯治に行ったりと、まあまあ豊かな生活環境は整っています。
とすれば、日本の「貧困」とは絶対的貧困ではなく、相対的貧困がより国民を苦しめてきたという仮説を、この「明暗」の中に見出すこともできるかもしれません(もちろん、東北の絶望的な飢饉や山本有三の「路傍の石」のような絶対的貧困の悲劇もあることは付け加えておきますが)。
従来の夫婦の問題ではなく、明治という激動の変化の社会、そしてその後の日本の悲惨な運命と令和時代の奇妙な相似性を鑑みながら、「明暗」の世界観を読み解くのも面白いのではないでしょうか。