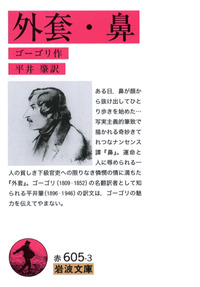読まないのは損なほど面白い「外套」

前2回では、ドストエフスキーとトルストイという世界史においても屈指の文豪を紹介した訳ですが、華やかで重厚なロシア文壇史を彩るのは彼らだけではありません。
ニコライ・ゴーゴリ(1809年4月1日 – 1852年3月4日)もまた、今日でも多くのファンを持つ、類まれな才能の持ち主でした。
というより、彼の場合は「鬼才」という誉め言葉の方が似合うでしょう。
人間の内面まで抉るようにリアルに描写したドストエフスキーやトルストイの筆致に対し、ゴーゴリは現実の中にきわめて空想的な展開を織り交ぜ、ロシア社会の不条理で救いようのない絶望感をかえって克明に描き出しました。
そんな彼の代表作が、「鼻」と「外套」です。
まず「鼻」ですが、一見、ふざけた小説にしか見えません。
サンクトペテルブルクの理髪師イワンは、朝、パンから八等官コワリョーフの鼻が現れる。イワンは鼻を捨てようと試みるが、失敗。コワリョーフは鼻を探し、新聞に広告を出すが無視される。鼻が戻った後、医師に治療を拒絶されるが、最終的に鼻は元に戻り、コワリョーフは幸せな日々を過ごす。
まあ大方、上のようなあらすじですが、シュールですね。コワリョーフの鼻は勝手に動き回って言うことを聞かず、時に役人より偉そうな振る舞いをします。それに翻弄される役人の滑稽さ!を読むに、まさにゴーゴリの官僚に対する強烈な風刺を感じずにはおれません。
さて、そんなゴーゴリの権力や人間の傲慢に対する厳しいまなざしは、よりリアルな形で次の「外套」に引き継がれます。
「外套」の主人公はアカーキー・アカーキエヴィッチ。下級役人であり、非常に限定的な「書記」の仕事に携わっています。彼は異動や昇進を望まず、また他の仕事を任せたら全くうまくいかず、まさにその仕事をするために生まれてきたような男でした。
ただし、その仕事ぶりは極めて真面目。仕上がりについても言うことがなく、本来ならば周りから尊敬の目で見られてもおかしくない人物です。
それなのに、周囲は素朴で不器用な彼をバカにし、読んでいて不愉快な気分になるほど酷い扱いをします。結局、アカーキー・アカーキエヴィッチはいつまでたっても下っ端のままで、結婚もできず、その日暮らしに甘んじていました。
ところが、そんな彼を奮起させる出来事が起きます。「半纏」と周囲から嘲笑われていた「外套」を新調することとなり、いろいろな経緯から彼は他人が羨むような「外套」を手に入れることができたのです…。しかし、それはアカーキー・アカーキエヴィッチの悲惨な人生に束の間の陽光が差す出来事でありながら、同時に悲劇の始まりでもありました。彼はいったいどうなってしまうのでしょう。
この作品は、政治的にも経済的にも行き詰まりを見せていた当時のロシア社会の悲惨な市民の暮らしをゴーゴリが独特の筆致で炙り出した傑作です。ただし、魯迅の「阿Q正伝」やゾラの「居酒屋」のような陰惨さはなく、ちょっと笑ってしまうようなブラック・ユーモアがあちこちに散りばめられていることもあって、読後感はカラッとしています。
また、外套を手に入れたアカーキー・アカーキエヴィッチのさらなる悲運のために、以前は彼をバカにしていた周囲が積極的に手を差し伸べたり、彼を叱責した有力者が自分の冷淡さをひどく反省したりと、後半は救われるような描写が続き、まるで人間を性善説でとらえようと言う作者の想いが伝わってくるようです。
そして何より、これまで何も得てこなかったし、今後も得ることのないような凡人(無力な庶民)が、「外套」を通して生き生きと生まれ変わる姿。そして、彼を貶めた様々なブルシットな人々と社会の狂騒を一つの作品の中に照射したゴーゴリの凄さには感服せざるを得ません。
最後に、鬼才ゴーゴリの諧謔的でブラックユーモアにあふれ、性善と性悪が織り成す歪な社会を描写した作品をもっと知りたい方は、ぜひ下記をご購入されることをお薦めします。後発のドストエフスキーとトルストイの作品をより深く味わうためにも、大きな助けになることと思います。